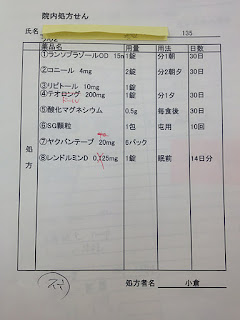7月~10月アタマの活動内容報告を挙げてみます。
ここに書いてある内容が活動の本質ではないと思うんですけどね。
形にするとこうなります。
もっとほんとは住民の人たちとこんな風に関わってこんなことがあって
こんな風に感じてこんな風に喜んでもらった~みたいなことが大事なんじゃないかと思います。
そんな話題はヒハ先生の記事からどうぞ読み取ってください。
写真は入釜谷地区のおじぞうさん。
ばあちゃん手編みの赤い頭巾がかぶされています。

<<三か月の活動内容(平成23年7月15日~10月8日)>>
【在宅支援】
地元河北地区総合支所保健師との毎日ミーティングの中で情報交換や新規依頼を受け主に訪問看護を中心に行い、在宅リハビリ、在宅診療を諏訪中央病院スタッフが行った。
◎訪問診察 15件
◎患者移送・受診介助3件
【診療】
石巻圏合同医療救護班からの依頼の元に無医村地区となった雄勝地区、入釜谷地区の診療。また石巻日赤本院の救急医療支援を行った。桃生郡医師会理事の石垣クリニックで診療支援も施行。
◎雄勝診療救護所 (9回 患者数?名)
◎雄勝診療所(1回3名)
◎入釜谷地区診療(2回 患者数約30名)
◎日赤救急当番(準夜9回, 深夜2回, 日直5回)
◎東松島石垣クリニック診療補助7回
【各種ミーティング】
医療「石巻圏合同救護チーム」、行政「石巻市役所・河北総合支所」、ボランティア「石巻復興支援協議会」等それぞれの代表組織とは密に連携をとって支援活動を継続。
◎石巻圏合同救護チームミーティング
◎河北支所 保健師との合同ミーティング
◎涌谷町国民健康福祉センター 青沼先生ミーティング
◎石巻専修大 復興支援協議会ミーティング
【コーディネート】
短期支援に関して現地コーディネーターの負担減を測った。
◎PT濱さん、上條さん、清水さん
◎高木先生、竹内先生、遠藤先生、伊藤先生受け入れ
【その他】
地元行事に参加する事、被災地生活支援を一緒に手伝う中で人間関係の構築、医師としてのニーズの拾い上げなどを行っている。被災地全体のステージとしては平成23年9月からは仮設住宅での生活とその支援が本格化している。
諏訪中央病院医師としては講演会などを主に担当。
◎仮設住宅支援「お茶っこくらぶ」5回
◎「川開き祭」救護所
◎避難所生活支援「ダニバスターズ」3回
◎瓦礫撤去1回
◎写真洗浄1回
◎千人風呂1回
【講演活動等】
・6/28 原小学校 被災地支援講義・ワークショップ(奥・原村保健師)
・7/05 原村柏木地区 いきいきサロン「石巻支援報告」(奥)
・8/24 石巻市河北地区で保健推進委員約50名に「放射線障害」講義(奥)
・9/01 原村生活習慣病予防研修会「生活習慣病・石巻活動報告」講義(奥)
・9/16 原村生活習慣病予防研修会「生活習慣病・石巻活動報告」講義(奥)
・9/20 石巻市多目的運動公園仮設住宅「すまいと健康」講義(遠藤)
・9/26 石巻市三反走仮設住宅「すまいと健康」講義(遠藤)
・10/3 石巻市追波川川前仮設住宅「すまいと健康」講義(遠藤)
・10/7 安国寺公民館「石巻支援報告」講義(奥・竹内)
【報道】
・6/29 長野日報
・7/23号 東洋経済
・8月号 諏訪郡医師会会報
・9/月 信濃毎日新聞
・9月 東日本放送(KHB)
・10月号 諏訪教育会会報
【活動の推移と見通し】
震災3カ月目の7月に本格的に被災地支援開始。被災地の壊滅的な状態は続く。医療に関わる状態としては急性期の「この集団をケアする医師がいない、薬がない」等の当初の問題から、「この人・この集団に関してはこういう問題」等の個別性の高い問題に変化していた。その中で「寄り添う支援医療」ということで一人1カ月単位の長期支援開始。
比較的長期、継続的に現地にいることができるということで仕事を任されるケースが増加し、引き継ぎ期間を平日5日間と十分にとることが現地の信任にもつながっていると考えられる。日本で唯一の単一医療機関からの家庭医療後期研修医長期派遣プロジェクトとして現在活動継続中。
業務内容は主に無医村地区となった雄勝地区・河北入釜谷地区の診療、石巻日赤救急支援、桃生郡医師会石垣クリニック診療補助、河北地区在宅支援等の診療活動に加え、避難所次いで仮設住宅支援として講演会などを行っている。
震災7カ月の10月現在、最も被災地の大きな課題となっているのは雄勝地区の医療体制再構築。9月に壊滅し医師が全員死亡したことで機能停止に陥っている雄勝病院の代わりに仮設診療所が9月にやっと完成。リアス式海岸内部のかなり入り組んだ山の広い地域に対して、新規に域外から常駐する事になった医師は一人のみで立ち上げに難渋している。現在伊藤医師は週4回程度雄勝診療所の診療+立ち上げ補助活動を継続している。見通しはかなり不透明であるが、今後1~3カ月程度安定までにかかる見込み。
【今後その他の活動】
・10/22 諏訪中央病院祭で”災害プロジェクト”運営
「鎌田名誉院長講演」「行政・消防・病院・石巻代表でシンポジウム」「森のナースの一次応急処置ワークショップ」「市役所の水道車出動」「食生活改善推進委員と炊き出し体験(豚汁、災害用炊飯)」
「暗闇で救出体験」「福島っ子の夏休み作品展示」「もし茅野にM8地震が起きたら」
「原小学校・東部中学校被災地へのチャリティーステージ発表」⇒ 石巻橋浦小学校 / 三反走仮設住宅住民との交流
病院祭での募金、収益金の一部は石巻へ寄付。
・看護部防災委員会を通して「もし茅野にM8地震が起きたら」アンケート結果提出。